資格確認書について
資格確認書について
紙の保険証は令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か資格確認書で受診していただくことになります。
取扱いの詳細は下記リンクを参照
資格確認書の記載内容について
令和7年8月1日から令和9年7月31日までご使用いただく資格確認書の色はだいだい色です。

なお、これまでの保険証に記載していた情報に加えて、申請により、下記の情報を追記することができます。
任意記載事項
限度区分
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて申請してください。
※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証の情報を記載した方を含む)申請によらず、限度区分を記載した資格確認書を交付します。
長期入院該当日
過去12カ月間で「区分II」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
※長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。
食事代などの詳細は下記リンクを参照
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止以降も引き続き使うことができます。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
※申請のない方等は任意記載事項が記載されませんので、該当部分が空白になります。
取扱いのご注意
- 資格確認書の交付を受けたときは、大切に保管してください。
- 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を提出してください。
- 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等ごとに一箇月につき、別に定められた額を限度とします。入院の際に食事療養又は生活療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となります。また、認定を受けた特定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごとに1箇月につき1万円を限度とします。ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることになります。
- 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに資格確認書を市区町村に返還してください。また、転出の届出をする際には、資格確認書を添えてください。
- 資格確認書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、資格確認書を添えて、後期高齢者医療広域連合あての届書を、市区町村に提出してください。
- 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することができません。また、有効期限を経過した資格確認書を使用して後期高齢者医療給付を受けた場合は、後期高齢者医療給付費の返還を求める場合があります。
- 後期高齢者医療広域連合の検認又は更新のため、資格確認書の提出を求められたときは、速やかに、市区町村に提出してください。
- 特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、資格確認書を返還していただくことがあります。
- 不正に資格確認書を使用した者は、刑法(明治40年法律第45号)により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
- 交付された資格確認書の記載内容を確認してください。内容を書き換えたものは使用できません。
- 受診後に病院に預けたりしないようにしましょう。
- 紛失したときは、市区町村窓口にて再交付の申請ができます。
- 一部負担金の割合欄等の記載に変更があったときは、市区町村窓口に古い保険証を返却してください(※)
※一部負担金の割合は、有効期限前でも世帯構成の変更や所得の更正に基づき変更になる場合があります。
資格確認書更新のご案内について
令和7年8月1日から令和9年7月31日までご使用いただく資格確認書の色は、だいだい色です。
令和7年一斉更新における資格確認書同封のご案内チラシはこちらをご参照ください。
-
「資格確認書」送付のお知らせ (PDF 1.6MB)

-
マイナンバーカードの保険証利用に関するチラシ(1) (PDF 1.7MB)

-
マイナンバーカードの保険証利用に関するチラシ(2) (PDF 1.3MB)

また、医療機関等に掲示しているポスターは、以下の通りです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500
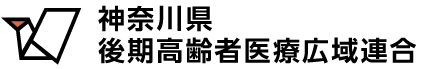
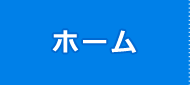
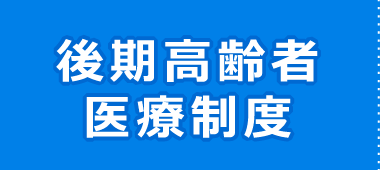
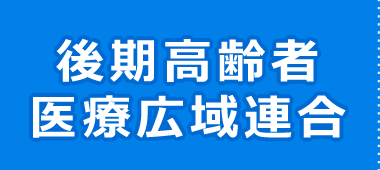

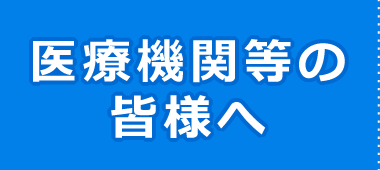
 保険証(加入・返却)
保険証(加入・返却) お医者さん等にかかるとき
お医者さん等にかかるとき 保険料について
保険料について 給付の内容
給付の内容 健康診査等
健康診査等 各種手続き(申請方法・様式集)
各種手続き(申請方法・様式集) よくある質問
よくある質問 困ったときは(相談窓口)
困ったときは(相談窓口)